
治療例 CASES
【検査シリーズ①】尿検査について
2024年10月8日(火)
【概要】
腎臓で作られた尿は尿管を通って膀胱に溜められ、尿道を通って排泄されます。結石症や膀胱炎など尿路系の疾患だけではなく、糖尿病や免疫系の異常など全身状態の把握にも有用です
【採尿方法】
| とりかた(例) | メリット | デメリット | |
| 自然排尿 | ペットシーツにラップをひき、自然尿を採取 | 動物の負担が少ない | 常在菌や膣、包皮内細胞の混入 |
| カテーテル尿 | 尿道カテーテルとシリンジで採尿 | 外部からの細菌などの混入がやや少ない | 感染の恐れ 雌は手技に慣れが必要 |
| 膀胱穿刺 | 経皮的に膀胱を針で穿刺して採尿 | 細菌混入のリスクが最も低い→膀胱炎の診断に最適 | 凝固異常や膀胱腫瘍を疑う動物には禁忌
|
※採尿から受診までに時間がかかる場合は冷蔵保存してください。
ただし12時間以上の保存では菌が死滅する可能性もあるため、
採尿できたら早めの受診をおすすめします。
採尿方法のリーフレットもご用意しております
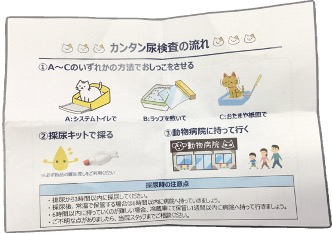
【一般尿検査】
尿性状検査:色、透明度、尿比重など
尿試験紙検査:pH、蛋白、尿糖、ケトン、血液、ビリルビンなど

※尿化学分析装置
この機械では、ブドウ糖、蛋白質、ビリルビン、潜血、pH、ケトン体、亜硝酸塩、白血球等様々な化学的性状を確認する事が出来ます。
これらを確認する事で、糖尿病や腎臓病の診断に役立ちます。
次にご紹介させて頂くのは『尿比重計』です。
尿比重を調べることで、腎臓での尿の濃縮力を知ることができます。
腎臓病の子では、尿比重は低くなる傾向にあります。
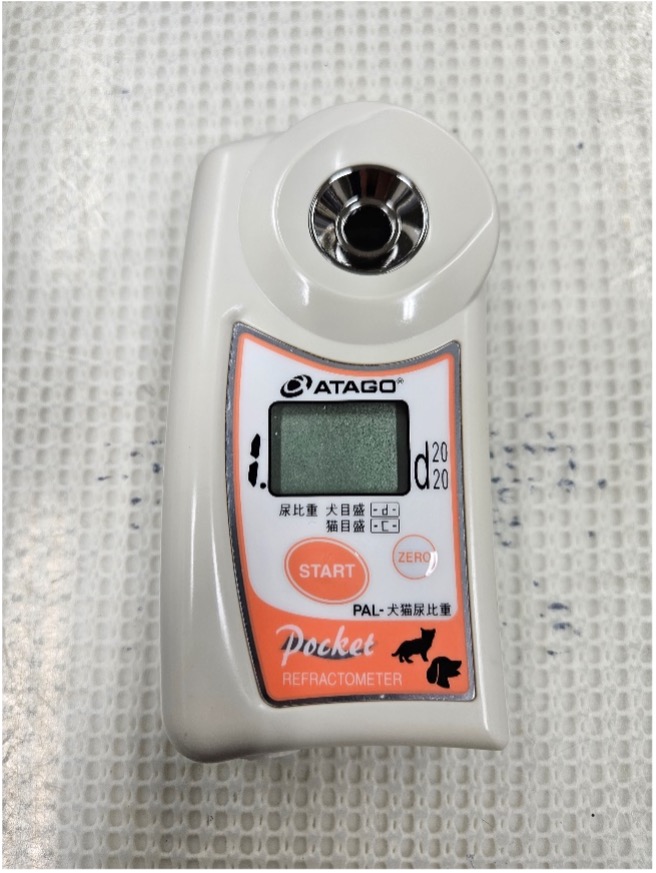
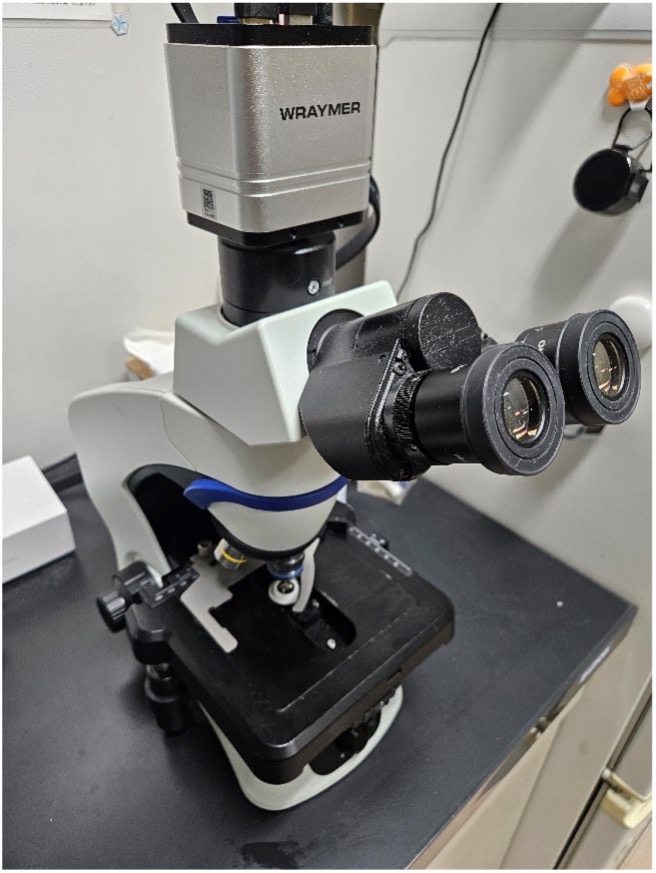
(下)ストルバイト結晶→結石症の疑い
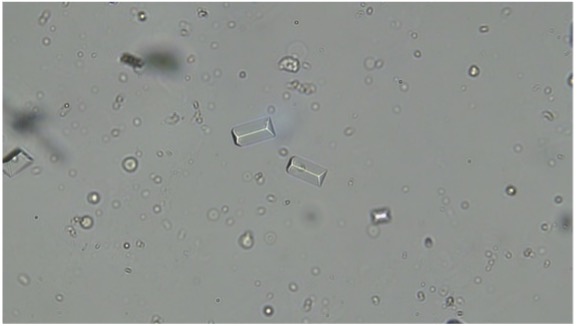
(下)上皮細胞

(下)赤血球と細菌→膀胱炎の疑い

最後にご紹介するのは『顕微鏡』です。
顕微鏡で尿を確認する事で、画像の様な結晶や、細菌の存在を確認する事が出来ます。
【まとめ】
院内で検査する以外にも、細菌尿であった場合には培養検査、尿蛋白が出ていた場合には尿蛋白/クレアチニン比など、外部の検査センターでしかできない検査もあります。尿検査をする事で、尿中にタンパクや糖、結晶、細菌等が出ていないを知ることができます。
最近尿の回数が増えた、トイレにきらきらしたものがついている、いつもと比べておしっこの色が薄い(あるいは濃い)等の症状が認められた場合はぜひ当院でご相談下さい。
獣医師 井戸俊佑/中西彩乃




